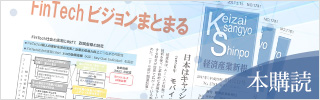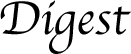
ダイジェスト詳細
デジタル空間に「デジタル共通基盤」を ~IPA理事長 齊藤裕氏に聞く

DXやGXが推進されつつある今、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が担う役割が非常に高まってきている。サイバーセキュリティやデジタル人材育成などを担い、「デジタルエコシステム」創設に取り組んでいる齊藤理事長にIPAの今後の役割と展望を聞いた。
デジタル社会創造のために
従来の我々は、産業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を担っていた。最近は、さらにデジタルを活用したイノベーション起こしや、AIセーフティの領域も入ってきた。国が整備すべき「デジタル共通基盤」を整備する役割を担う段階に入ってきた。さらに、その基盤を活用して「デジタル社会」を創造していかなくてはならない。そこには、安心・安全を確保する必要がある。また、サイバーセキュリティやAIセーフティの重要性も高まっている。
資本市場で自由闊達に発展させていく形態を、サイバー空間の中に形成させていかなければならない。従来、日本にあった個別の領域でなく、エコシステムのようなもので企業を連携させていくのがIPAの役割であろうと、私が言い始めたミッションだ。
私がIPAに来る前、安倍首相の時の総合科学技術・イノベーション会議の時に、Society5.0について「あらゆる社会がデジタル化してくる」「企業の業務がデジタルで合理化されてくる」「社会にも同様のデジタル化が必要だ」との議論が始まった。そこには、あらゆるものを包含するデジタルアーキテクチャーが必要で、当時の西山圭太商務情報政策局長がIPAに「デジタルアーキテクチャセンター(DADC)」を作られた。私はそのセンター長を引き受けた。現在も兼任しているが、アーキテクチャーを作っても、そのデジタル基盤がないと動かない、その運用はやはり、IPAが担うべきとなってきた。当時のIPAにはIT人材センターも社会基盤センターもあり、セキュリティセンターもあった。
企業のビジネス領域と産業のインフラ領域も事業対象だ。IPAがサイバーセキュリティやトラストを含めた「デジタル共通基盤」のベースになれる。そう考えて、理事長をお引き受けした。
AI活用社会でますますAI赤字が膨らむ
――産業のDXを進めると「デジタル赤字」(年6兆円)がますます増える?
現在さかんにAI活用が言われている。AIを活用すると、目の前にサービスが提供され、仕事が効率的にいろいろなことが出来る。活用すればするほど、「自分の部下やコンサルはいらないな」という気持ちになる。知識も溜まってくる。
AIの部下がいれば、人間の部下が必要ないかもしれない。部下を育てて、自分がいなくても仕事が出来るように教育していたのが、AI・デジタルの世界で実現できるかもしれない。これがAI活用社会なのだ。
企業の管理者は要るが、100人いた部下は10人で済む。利益が上がるかも知れないが、従業員に支払った給料は、すべて海外のAIサービスに吸い取られてしまう。だからAI活用すると、企業の利益の大半がGAFAMのようなプラットフォーマーに持っていかれる。AI赤字はこれからも増え続けていくのは間違いない。もっと厄介なのが、経済安全保障の世界だ。日本の紙の世界の技術情報がデジタル化されると、日本国内にデータセンターがない限り、日本の強かったモノづくりの知識やノウハウなどが流出してしまう恐れがある。
日本型のデジタル共通基盤が必要だ
ここが日本のコアの課題だ。ある意味、日本にプラットフォーマー的な「デジタル共通基盤」を作らなければいけない。だからアーキテクチャーを設計するDADCに経産省はウラノスエコシステム・イニシアチブを立ち上げたと考えている。
日本社会はそれぞれの企業の活動で社会が構成されている。デジタル空間の中に、例えば、高速道路や鉄道のように、デジタルで共通に使える基盤があれば、とても便利になる。ある事業領域を固めて、共通で使えるところは協調領域を決めて、データ共有やサービス連携などが楽になる仕組み作りがウラノスエコシステムなのだ。協調領域を今プラットフォーマーとして展開しているのがGAFAM。ここにデータから何もかも依存するのはダメだ。全て取られてしまうので、「公共的・公益的に日本の中にデータ共通基盤を作ろう」と考えているのがウラノスだ。
この運用は、やはり、経済安保の観点から、ガバナンスの効く日本のきちんとした企業に担ってもらわないと困る。そこに、これからAI活用が入ってくる。処理自体がLLM(大規模言語処理)となってくると、巨大なデータセンターが必要になってくる。日本に巨大なデータセンターが必要になってくる。
最終的には、エネルギーの問題になってくる。皆がAIを使うようになると、よりマイクロサービス的なAIを構築し、インテグレーションしていく世界となる。
モノづくりの世界で無理、無駄をトコトン改善したように、デジタルの世界・サイバー空間の中でも「デジタル共通基盤」の中で最適化された社会を目指す。そこを支援していくのがIPAの役割なのではないだろうか?
(詳細は経済産業新報・本紙で。電子版試読キャンペーン実施中。)