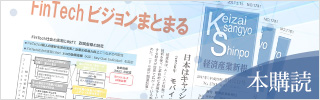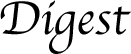
ダイジェスト詳細
世界の窓 “火の国“アゼルバイジャン 発展著しく、南コーカサス地域のリーダー国に

昨年11月、バクーでCOP29が開催された。バクー市の名前は知っていてもアゼルバイジャンの国の首都だと知っている人は少ない。34年前、旧ソ連から独立し、現在は、南コーカサスの地域リーダー国として存在感を増している。「世界の窓」第1回は、“火の国”アゼルバイジャン共和国G・イスマザイルザーデ大使を訪ね、今後の日本との関係をどう深めていくのかを聞いた。
2030年に再生エネルギー30%を約束
世界で一早い油田開発、安定している民主主義
アゼルバイジャンは、南コーカサスの真ん中に位置するカスピ海と黒海の間にある、面積1000万平方メートル(北海道と同等位)に人口1千万人が暮らす温暖な国だ。

「イスラム国では最初の、民主主義を掲げ、女性の投票権などの憲法を持つ国として建国され、多様な民族が共存する国家でした」。不幸なことに、それから70年間、ソ連に占領されてしまった。その理由は、石油です。1848年、世界で最初の油田をノーベル財団が開発したのがわが国です。その資源を丸ごとソ連に持っていかれました」。
1991年、ソ連の崩壊とともに独立を果たし、初代アリエフ大統領が誕生、その国を一番早く承認したのが日本だった。だから、親日の人が多く住んでいる。当時、9割を石油資源に頼って国づくりをしました。
しかし。大統領は「資源はいつか枯渇してしまう。その利益を他の産業を育てて、持続的成長のできる国にしよう」と考えた。
現在、ロシアとウクライナが戦争をしていて、欧州は資源不足で困っているそれを、陰で支えているのがアゼルバイジャンなのだ。
「カスピ海の海底油田からパイプラインで石油や天然ガスを欧州10カ国に送り続け、EUにとってはセキュリティ上、最も重要な国となっている。そのパイプラインの鉄管作りに投資してくれ、建設してくれたのが日本の伊藤忠さんです」。
原油が1990年代は第2次ブームとなり、当初1バレル=30㌦だったものが70㌦となって、国は豊かになった。世界の石油の0・7%、ガスの0・9%のシェアを誇っていた。
そこで、イルハム・アリエフ大統領は2030年までに再生エネルギーの比率を30%にするビジョンを打ちだした。温暖な地域なので、太陽光や風力の力を入れ、その再生エネルギーをまた欧州に送ろうと考えた。
構想の第1は農業とサービス、第2は原油を基に化学分野、第3にIT・ソフトウエア、宇宙に重点戦略とすることを決めた。今は人工衛星の打ち上げにも成功している。
北はロシア、南はイラン、西にトルコ、東には南コーカサスのジョージア、アルメニアとウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタンと国境を接している。
紀元前より、ローマ帝国や中国をつなぐユーラシア大陸のクロスロードに位置し、東西文明が交流するエレメントがあるCOP29の開催地に選ばれたのも、再エネルギーに取り組む、成長著しい地域のリーダー国である点が高く評価された。
「わが国の強みは、隣国アルメニアとの紛争時に避難民からスターとしたことです。そのため、「自給自足」の経済基盤を確立し、各国と平和条約を結びどの国とも交渉でき、友好関係を築いている」。
カスピ海の最大の港、バクーでは、東西物流の拠点として発展し、数々のスポーツイベントやユネスコの会議など国際イベント催される。
日本の富士山や古墳の堺市が世界遺産に選ばれたのもバクーだった。

「日本人の勤勉さ、人々の優しさ、おもてなしの精神は、とても尊敬されており、チームワークが素晴らしい。わが国は柔道、空手など個人競技が得意です。お互いにもっと交流し、関係を深めていきたい」。
アゼルバイジャンは、ワインが有名で、農業が盛んだ。政治も治安もよく、安定している。日本のアニメや漫画が好まれている。
「21世紀の国際関係は民間同士の連携が不可欠だ。日本はもっと産業への投資をして欲しい。まだ51 社しか進出していないのは残念だ。今後、再生エネルギー国家を目指すので、日本から技術を学びたい」。
大使の話を伺いながら、孫氏の兵法の「遠交近攻」の計を思い出した。遠い国と親しくして近くの国を攻略する。こんな親日国がいれば、国際会議でも日本の意見に賛同してくれる味方がいるのは心強い。民間交流をもっと進めるべき国であることが理解できた。
(詳細は経済産業新報本紙で)